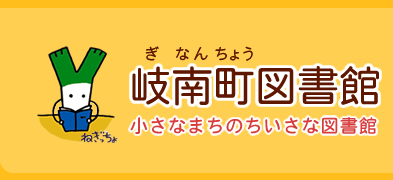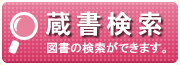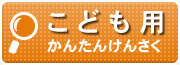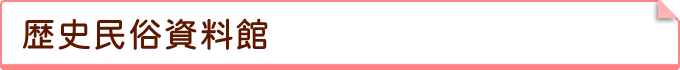HOME 歴史民俗資料館
歴史民俗資料館
岐南町歴史民俗資料館へようこそ
利用案内
| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時 |
|---|---|
| 休館日 | 図書館の休館日 |
| 入場料 | 無料 |
| 場所 | 図書館に併設しています。図書館内から資料館へ入退館できます。 |
旧宮川家 住宅一棟附 生活用具一括(岐阜県重要無形民俗文化財)

旧宮川家住宅は明治26年(1893)、現在の徳田6丁目に濃尾震災(1891)後に建てられたものを、昭和54年(1979)に現在の場所に移築しました。
農家建築として代表的な茅葺家屋で、間取りは八畳間四室を田の字型に配列し、襖などの仕切りを外すことで広間にできるなど、多用途に使えます。また、にわとりの止まり木、わら打ち石、かまど、五右衛門風呂などが極めて良い状態で保たれています。
明治時代の中期以後から昭和時代中頃までの、岐南町及びその周辺地域の生活様式を知ることが出来る貴重な建築物です。
開館時間:午前10時~午後4時
※悪天候等の理由により室内をご覧できない場合がございます。
資料館

歴史民俗資料館では、稲作を中心とした農耕具やかつての重要な産業であった養蚕具、明治時代以降の生活用具を常設展示しています。
薬草木庭園

岐南町図書館・歴史民俗資料館の駐車場南側には、四季折々、季節の花が小さな庭園を彩っています。
辻󠄀門

この辻󠄀門は岐南町伏屋の旧住宅正門を移築したものです。江戸時代の様式を持っていますが、明治中期の建造で、瓦は、明治末期の頃のものと思われます。
門は形態によって呼称が異なっており、また、地方によっても異なっています。辻󠄀門は、太い同じ柱が4本で上に屋根がある四脚門より柱が細いものです。
門の戸には、良いものは、飾り金具が多く付けられていますが、この辻󠄀門は少ないです。
文化遺産として価値が高いとして岐南町図書館・歴史民俗資料館の駐車場へ移築されました。
竣工年月日:平成8年5月31日
岐南町発行図書の販売案内
| 書名 | 価格(円) | |
|---|---|---|
| 民俗資料集 | Ⅰ 養蚕具・織機編 | 1,000 |
| Ⅱ 農耕具編 | 1,000 | |
| Ⅲ 生活用具編 | 在庫なし | |
| Ⅳ むかし話とむかしのくらし編 | 在庫なし | |
| Ⅴ 長屋門編 | 在庫なし | |
| Ⅵ 伏屋の獅子芝居編(改訂版) | 1,100 | |
| Ⅶ 境川のむかしと今 | 1,200 | |
| Ⅷ ふるさとの神社・仏閣と祭 | 1,200 | |
| Ⅸ ふるさとの方言と遊び | 800 | |
| Ⅹ ふるさと岐南 地名物語 | 1,000 | |
| 岐南町史 | 通史編 | 4,500 |
| 資料編 | 3,300 | |
| 写真集 | ふるさと | 2,000 |
| 戦時の回想 | 1,200 | |
購入を希望する方は、岐南町図書館・歴史民俗資料館へお間い合わせください。販売価格+送料を現金書留でお送り頂いた後に発送致します。
岐南町内の文化財
伏屋 の獅子芝居 (岐阜県重要無形民俗文化財)

伏屋の獅子芝居 動画(4分27秒)
伏屋の獅子芝居は、伊勢大神楽を発祥とした嫁獅子の流れを汲みます。
江戸時代後期の寛政年間に、三河で獅子芝居の原形が考え出され、天保年間に今日の嫁獅子の開祖と伝えられる市川竜介が現在の形を完成させました。明治時代には、伏屋の東五郎が近村を上演して回り、昭和時代にも弟子が県内を巡業するなどして活躍しました。
獅子舞は、「道行」、「寄」に続いて「神楽獅子」の悪魔祓いに移り、幕の舞、幣の舞、上の舞、下の舞と演じられます。最後に、獅子頭を被った演者が女形になって獅子芝居を演じます。
- YouTube岐南町公式チャンネルにて動画「岐南町 伏屋の獅子舞」をアップしています。
YouTube岐南町公式チャンネル
(別ウィンドウで開きます) - 地芝居大国ぎふWebミュージアム 地芝居ヒストリアにて、インタビュー動画【地芝居を支える】岐南町伏屋獅子舞保存会会長 朝倉修一が掲載されています。
- 地芝居大国ぎふWebミュージアム
(別ウィンドウで開きます) - 【地芝居を支える】担い手インタビュー
日本語版
多言語字幕版
(別ウィンドウで開きます)
- 地芝居大国ぎふWebミュージアム
飯沼勘平長資 の墓

飯沼勘平長資は下総の国(現在の千葉県)から出た源氏の子孫で、通称小勘平と言い、その時の岐阜城主であった織田秀信に仕えていた武将でした。
慶長5年(1600)8月、関ケ原合戦の前哨戦となる戦いが、現在の笠松町米野から岐南町平島の一帯でありました。西軍に加わった秀信は木曽川の北岸(現在の各務原市川島と笠松町米野)に陣を取り、東軍を迎え撃ちました。長資は平島付近に配置され、東軍の武将、大塚権太夫を倒すなどの手柄を上げましたが、東軍の大将である池田輝政の弟、池田長吉と槍を合わせて果敢に戦い戦死しました。8月22日、長資21歳の時でした。
村上彦四郎善光 ・妻岩根女一族 の墓

村上彦四郎義光は、鎌倉時代末期の信濃(現在の長野県)の武将で、後醍醐天皇第二皇子の護良親王(大塔宮)の忠臣でした。
義光は親王のお召しにより、信濃から吉野(現在の奈良県)に向かう途中、現在の上印食と下印食の境あたりにあった才(西)海寺に住んでいた乳母をたより、妻の岩根を預けて吉野に向かいました。
元弘3年(1333)、鎌倉幕府が吉野を攻めて大激戦となりました。護良親王が絶体絶命となった時、義光は親王のお召し物をまとい、身代わりとなって華々しい最期を遂げました。義光の戦死を知った乳母は近くの池に身を投げ、妻もこの地で亡くなりました。
義光が戦死した29年後の康安2年(1362)、才海寺に義光と妻の一族の供養塔が建てられましたが、江戸時代初期に才海寺は廃寺となり、現在の地に移されました。
伏屋城跡

伏屋城は、織田信長が羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)に命じて構築したものですが、その時期は明らかになっていません。
徳川家康と秀吉が戦った天正12年(1584)の小牧・長久手の戦いにおいては、伏屋市兵衛に書状を出して留守居を命じており、秀吉の一番北の砦であったと考えられています。
当時の伏屋城は、土塁(砦の周囲に土を高く固めて積み上げ構築したもの)・堀・館といった程度のものでしたが、戦いが馬と人を中心にして行われた時代であり、充分に基地の役割を果たしていました。
現在は、当時の土塁の一部が残っています。
円空作仏像 三体

円空上人は寛永9年(1632)に美濃の国中島郡中村(現在の羽島市)に生まれました。(郡上市美並という説もあります。)
円空上人は、江戸時代初期の造像僧として知られ、その作品は美術的に高い評価を得ています。飛騨や尾張、遠くは蝦夷地までも旅をして、全国に数多くの仏像を残しています。
平成27年までは、円空上人の彫った仏像や神像は、「なた彫り」と言われる荒けずりのものですが、どれも微笑みのある穏やかな表情をしております。三宅の如意寺には「合掌像」「大黒像」「神像」とされる3体の像が所蔵されていましたが、現在は岐南町に寄託されて岐南町歴史民俗資料館が保管しています。
円空作仏像 一体

岐南町徳田の個人宅には「大日如来像」といわれる円空上人作の仏像が1体所蔵されています。
円空上人は、旅する道中、宿泊した神社や民家に宿代の代わりとして彫った仏像を残していくことが多くありました。所蔵する御宅がかつて徳田村で庄屋をつとめていた際に、旅の途中の円空が宿を取り、一宿一飯のお礼代わりに残した仏像であろうと思われます。
お囲 い堤

お囲い堤は、旧三宅村から笠松町米野に至る堤で、かつて「高道」と呼ばれる村堤と道を兼ねたものでした。
江戸時代初期の寛文元年(1661)、野中村は尾張藩の成瀬豊前家の知行地になりました。それ以後境川(現在の木曽川)の氾濫や、各務原台地からの流れを防ぐため、たびたび高道をかさ上げして、堤を高くし洪水を防ぎました。
これにより、野中をはじめとする水下の村々に利益をもたらしましたが、反面、平島村、中島村などの水上の村々との争いのもととなりました。
現在は、土地改良によってわずかを残すのみですが、旧村の地形を証明する史跡です。
エノキ

エノキはニレ科の落葉高木で、本州中部以南の山野に分布します。古くから街道の一里塚の目標樹として植えられてきました。
●樹齢/約210年(令和7年8月現在)
●樹高/17.32メートル
●幹回り/3.52メートル
※指定時の樹齢/約160年
※樹高及び幹回り:平成29年調査
豊松清十郎 の墓

初代豊松清十郎は、人形浄瑠璃・大阪文楽の女形人形遣いです。
幕府は財政建て直しのため、江戸時代後期の天保12年(1841)から3年間、芝居の廃止を含む改革令(天保の改革)を出しました。これにより、大阪では文楽の上演が出来なくなりました。
清十郎は知人をたよりに名古屋に来ましたが、岩田善六という義太夫の愛好者がその芸風に惚れ込み、三宅村に招いて厚くもてなしました。清十郎はこれに応えて三宅村に移り住み、近所の人々に人形遣いの技法を教え、「三宅文楽」の始まりとなりました。
その後、豊松清十郎はそのすぐれた芸風で東海地方一帯に一座を率い、その名を謳われましたが、明治4年(1871)、浜松での興行中に亡くなりました。三宅の人たちは、清十郎の墓石を建て今も供養を続けています。
三宅文楽

三宅村では300年以上前の江戸時代に「あやつり」という人形芝居が行われており、操り芝居の好きな多くの人が、仕事のあい間をみては習っていました。
豊松清十郎による人形遣いの技法の伝授により、三宅文楽は盛んに行なわれましたが、大正元年(1912)頃、後継者が無くなり途絶えました。
昭和20年(1945)頃まで三宅には、当時使われていた、人形の頭が約30首の他に、人形の衣装も多く残っていましたが、現在は3軒の家に2首ずつ、計6首が残されています。
松原家 長屋門

長屋門は、岐南町で多く見受けられる建物です。
松原家の長屋門は江戸時代末期の建造で、明治8年(1875)頃、現在の場所に移築されました。この長屋門は、入り口の上にある木鼻の装飾が優れており、扉や柱は欅造りで美しい木目を見ることができます。
明治24年(1891)の濃尾地震では倒壊を免れました。その後、平成18年(2006)には、老朽化対策及び耐震補強のために修理を行い、令和7年(2025)には、東側の白壁の漆喰を塗り直して現在に至っています。
伏屋 の地芝居衣装

獅子芝居や地歌舞伎など、地域の人々によって行う芝居は「地芝居」と呼ばれています。
伏屋の地芝居衣装は江戸時代後期から明治時代中期にかけて制作されたものとみられます。高度な技術で作られたものも含まれており、岐南町伏屋獅子舞保存会が現在所有している地芝居衣装のうち、特に貴重な14点が有形民俗文化財に指定されています。
写真は明治初期に、高位の花魁役が着用した「
- 有形民俗文化財に指定された衣装の一覧[PDFファイル] (別ウィンドウで開きます)
文化財一覧
| 名称 | 所在地 | 時代・ 幹の周囲 |
種別 | 指定年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 旧宮川家住宅一棟附 生活用具一括 |
平成 歴史民俗資料館 |
明治 | 有形民俗(建造物) | 県 昭和55年3月25日 |
| 伏屋の獅子芝居 | 伏屋 | 江戸 | 無形民俗 (芸能) |
県 昭和63年8月23日 |
| 円空作仏像三体 | 平成 歴史民俗資料館 |
江戸 | 有形(彫刻) | 昭和53年11月15日 |
| 円空作仏像一体 | 徳田 | 江戸 | 有形(彫刻) | 平成3年7月25日 |
| 松原家長屋門 | 薬師寺 | 江戸 | 有形(建造物) | 昭和62年2月17日 |
| 三宅文楽人形の頭 | 三宅 | 江戸 ~ 明治 |
有形民俗 (芸能) |
平成2年1月17日 |
| 村上彦四郎義光公・ 妻岩根女一族の墓 |
八剣 河野専光寺 墓地 |
鎌倉 | 史跡 | 昭和53年11月15日 |
| 豊松清十郎の墓 | 三宅 三宅浄苑 |
江戸~ 明治 |
史跡 | 昭和53年11月15日 |
| 飯沼勘平長資の墓 | 平島 | 江戸 | 史跡 | 昭和53年11月15日 |
| 伏屋城趾 | 伏屋 | 安土桃山 | 史跡 | 昭和54年9月5日 |
| エノキ | 上印食 生島神社参道 |
江戸 3.52m |
天然記念物 | 昭和53年11月15日 |
| お囲い堤 | 野中 | 江戸 | 史跡 | 昭和53年11月15日 |
| 伏屋の地芝居衣装 | 伏屋 獅子舞会館 |
江戸~ 明治 |
有形民俗 (衣装) |
令和4年4月4日 |